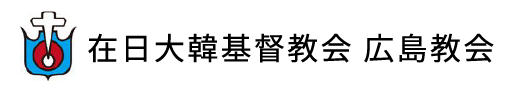2025年02月02日 主日礼拝 式順・説教
2025年2月2日 主日礼拝 式順・説教
〇黙 祷
〇招 詞 詩編(시편) 5編 3~4節
〇讃 頌 讃頌歌 12
〇信仰告白 使徒信条
〇祈 祷
〇交 読 文 交読文 9 (詩編 15編)
〇讃 頌 讃頌歌 214
〇聖書奉読 マタイによる福音書(마태복음)
8章 18~22節
〇説 教 「主イエスに従うとは
(주 예수를 따른다는 것)」
〇祈 祷
〇讃 頌 讃頌歌 218
〇奉献祈祷
〇献 金
〇交 わ り
〇頌 栄 讃頌歌 6
〇祝 祷
※ 説教映像をYouTubeでご覧いただけます。
【 2025年 2月 2日 主日礼拝説教(要約版)】
「主イエスに従うとは」
マタイによる福音書 8章 18~22節
イエスさまが山を下りられてから、悪霊を追い出し、病を癒やした、そのイエスさまの御業を目撃した人々が熱狂してイエスさまのもとに集まってきました。イエスさまは自分を取り囲んでいる群衆を見て、弟子たちに向こう岸に行くように命じられました。
熱狂している群衆というのは、とても危険な常態かと思います。気分が高揚して一時群がりますが、それもしばらくの間だけです。引き潮のように引いて行きます。それで終わればまだ良い方で、今度は敵対勢力になって押し寄せて来たりもします。
イエスさまのもとに群がった人々も、イエスさまの教えや癒やしの業を見て、この方こそ自分の願いを聞いてくださる方だと思い、集まっているわけですが、イエスさまはそれを危険と見なしたのでしょう。自分の身が危険だと思ったというよりは、自分の目的、自分の願いとは違う方向に向かっているように感じたのでしょう。そこで、イエスさまは熱狂する群衆と距離を置くために、ガリラヤ湖の向こう岸へ渡ることを弟子たちに指示しました。群衆からの分離は、必然的に真の弟子とは誰なのか、明らかになる時です。今日の聖書箇所がその物語です。興味本位の人、
ついて行く意志の弱い人はふるわれ、誰が本当の弟子なのか、ある程度明らかにされ、その人数はしぼられていきます。
その群衆の中に、ある律法学者がおりました。彼はイエスさまの言葉を聞き、イエスさまの御業を見て、最高の先生に出会えたと感激があったのでしょう。その先生がどこかに行ってしまわれます。彼は思わず、「先生、あなたがおいでになる所なら、どこへでも従って参ります」(19節)と言いました。この言葉に偽りはありません。律法学者はユダヤ教の教師であり、民の指導者です。そんな人がイエスさまについて行くと言います。しかも、カファルナウムから見て、ガリラヤ湖の向こう岸というのは、異教の地です。ユダヤ教の教師が異教の地に行くというのは、並々ならぬ決断が、そこにはあります。
しかし、イエスさまは「「狐には穴があり、空の鳥には巣がある。だが、人の子には枕する所もない」(20節)と答えられました。
このイエスさまの答えは、律法学者の求めに直接答えたものになっていません。一体、イエスさまのこの言葉は、何を意味しているのでしょうか。
この律法学者はイエスさまに「先生」と呼びかけております。彼はイエスさまに夢中になっておりましたが、聖書を学ぶ上で最高の教師であるという認識でした。イエスさまはその心を見抜いておられたのでしょう。そのため、彼の申し出に対して直接返事をすることを控え、彼の心をテストする言葉を投げかけました。「狐には穴があり、空の鳥には巣がある。だが、人の子には枕する所もない」と。
このイエスさまの言葉は、簡単に言いますと、「どんなに多くの犠牲を払うとしても、私に従う覚悟はあるのか」と言うことです。この律法学者は一見すると、犠牲を覚悟しているようにも思えます。でも、狼の中に送り出される羊になることを理解していません。家族に反対されても従わなければならないことを知らないのです。イエスさまに従うということが、ゲッセマネ、ゴルゴダ、そして墓にまで従わなければならないことを理解しておりません。
この時、側近のペトロやヨハネさえもそこまでは理解していなかったかも知れず、彼にその理解まで求めるのは酷かも知れません。しかし最低、「狐には穴があり、空の鳥には巣がある。だが、人の子には枕するところもない」ということを理解しなければならなりませんでした。彼には、ちょっと頭を冷やす時間が必要であったのです。
私たちもイエスさまに従う時に、犠牲を覚悟しなければならないと言われれば、躊躇してしまうでしょう。当然です。幸せになりたいと思ってイエスさまに従おうと思っているのですから、躊躇するのは当然です。ただ、これだけは言えます。本当の弟子は、たとい全世界を手に入れたとしてもイエス・キリストを失ったら空しいと知っているということです。イエスさまが永遠の命そのものであり、神御自身であると知っており、その価値を知っているからこそ、喜んで犠牲を払うことが出来ます。この先、どんなことが起こるのか分かりません。でも、イエスさまが共におられる。そのイエスさまの御手にすがりつくことが出来ると信じているのです。
それから、イエスさまがどのようなお方であるのか、ある程度しっかり理解しており、イエスさまに従うことを望んでいた一人の「弟子」がイエスさまにこう言いました。「主よ、まず、父を葬りに行かせてください。」(21節)
これに対し、イエスさまはそれを許さず、すぐについて来ることを命じます。「わたしに従いなさい。死んでいる者たちに、自分たちの死者を葬らせなさい。」(22節)
皆さん、この父親の葬りをめぐってのここでの会話は、どう理解したら良いのでしょうか。
私たちも親の葬儀を執り行うのは、子どもとしての義務だと思っています。ましてやユダヤ人にとっては、親を葬ることは至上命令でした。親を葬るのは、何も葬儀のことだけを意味しているのではありません。当時のユダヤ社会では、長男は親が亡くなって財産を相続するまでは、親を助けるために家を離れることが出来ませんでした。それが常識でした。ですから、この「父を葬りに行かせてください」というのは、「親を葬るまでは、家にいさせてください。親が亡くなってからついて行きます」ということなのかもしれません。つまり、この弟子は事実上、イエスさまに従うことを先延ばしにしたのです。そのため、イエスさまは「わたしに従いなさい」と、従いたいと願うのであれば、日を延ばさず、今、決断しなさいと言われているのです。
それにしても、イエスさまはこの弟子に従うことを促す際に、不思議な表現を取られています。22節です。「死んでいる者たちに、自分たちの死者を葬らせなさい。」
イエスさまは親の葬りを軽んじているのではないでしょう。ただ、その弟子はイエスさまに従う決心をする以前に属していた世界が、もはや自分の居場所ではないことを、はっきりと自覚しなければなりませんでした。
「死んでいる者たちに、自分たちの死者を葬らせる」とは、彼がかつて属していた世界は、罪のために死に定められている世界であるということです。イエスさまに従うというのは、神さまが人を滅びの定めから救い、命へと移されたことから生じる、人の側からの応答です。ですから、救いを得るためには、まず、何よりも神さまが救い主として世に送られたイエス・キリストを第一とすることが、すべての人に求められます。
この世のしがらみに囚われ、永遠の命を得ることを先延ばしにしている人を、イエスさまは「死んでいる者」と表現しているようです。イエスさまに従うというのは、何があってもひたむきにイエスさまと共に歩むことです。それを信仰と言います。
信仰とは決断です。私たちは、自らに対して「イエスに従う決意があるのか」ということを問い続けていかなければなりません。
しかし、ここで忘れてはならないのは、この「決断」や「決意」の根拠は、私たちの中には全くないのだということです。主イエス・キリストご自身による招きとしての「決断」と「決意」に基づいてはじめて成立することだということです。ここを忘れたら、私の信仰は自分たちの持ち物のように自分勝手に用いてしまうような、自分の都合のいい時だけの自分勝手な信仰に陥ってしまうのです。
日本では、信仰(宗教)というのは、心に安定をもたらしたり、人生に教訓を与えてくれるから良いものだと評価しますが、宗教に入れ込んではいけないと考える人が多いようです。確かに、危険な、深入りしてはいけない宗教というものもあるだろうと思いますが、本来、信仰というものは深入りしないで信仰とはいいません。「信じる」のですから、その点では理屈を越えるのです。本当に神さまを信じたときには人生観ばかりでなく、日常生活にも変化が起こるものです。キリスト教信仰の根本は、神さまが私たちを死者の世界から根こそぎ引き抜いてしまって、イエスさまに従って神の国に生きる者とされたことにあります。
皆さん、律法学者のように自分本位な思いからではなく、また一人の弟子のようにこの世のしがらみに後ろ髪引かれながらでもなく、イエス・キリストこそ命の道と信じ、ひたむきにイエスさまに従いつつ、共に歩んで行きましょう。
【2025년 2월 2일 주일예배(요약판)】
“주 예수님을 따른다는 것”
마태복음 8장 18~22절
예수님께서 산에서 내려오신 후, 귀신을 쫓아내고 병든 자를 고치셨습니다. 이러한 예수님의 기적을 목격한 사람들은 열광하며 예수님께 몰려들었습니다. 예수님은 자신을 둘러싼 무리를 보시고, 제자들에게 호수 건너편으로 가라고 명하셨습니다.
열광하는 무리는 매우 위험한 상태라고 할 수 있습니다. 감정이 고조되어 잠시 몰려들지만, 그것도 잠시일 뿐입니다. 마치 밀물이 들어왔다가 썰물처럼 빠져나가듯이 사라집니다. 그렇게 끝나면 다행이지만, 때로는 적대 세력이 되어 다시 몰려올 수도 있습니다.
예수님께 몰려든 사람들은 예수님의 가르침과 치유의 기적을 보고, 자신의 소원을 들어줄 분이라고 생각하여 모여든 것이었습니다. 그러나 예수님은 그것이 위험하다고 판단하셨습니다. 자신의 신변이 위험해서라기보다는, 그들의 기대와 자신의 사명이 다르다는 것을 느끼셨기 때문입니다. 그래서 예수님은 열광하는 무리와 거리를 두기 위해, 갈릴리 호수 건너편으로 가도록 제자들에게 지시하셨습니다. 이 과정에서 누가 진정한 제자인지가 분명해집니다. 호기심으로 온 사람들, 따를 결심이 약한 사람들은 걸러지고, 결국 참된 제자가 누구인지 어느 정도 드러나며, 그 수는 줄어들게 됩니다.
그 무리 중에 한 서기관(율법학자)가 있었습니다. 그는 예수님의 말씀을 듣고 기적을 목격하며, 최고의 선생님을 만났다는 감격을 느꼈을 것입니다. 그런데 그 선생님이 떠나려 하십니다. 그는 충동적으로 말했습니다.
“선생님이여 어디로 가시든지 저는 따르리이다.” (19절)
이 말에는 거짓이 없었습니다. 서기관은 유대교의 교사이자 백성의 지도자입니다. 그런 사람이 예수님을 따르겠다고 한 것입니다. 게다가 가버나움에서 볼 때 갈릴리 호수 건너편은 이방인의 땅이었습니다. 유대교 교사가 이방 땅으로 간다는 것은 큰 결단이 필요합니다.
그러나 예수님께서는 이렇게 대답하셨습니다.
“여우도 굴이 있고, 공중의 새도 거처가 있으되, 인자는 머리 둘 곳이 없다.” (20절)
이 말씀은 서기관의 요청에 대한 직접적인 대답이 아니었습니다. 예수님께서 이 말씀을 하신 의미는 무엇일까요?
서기관은 예수님을 "선생님"이라고 불렀습니다. 그는 예수님께 열중했지만, 단순히 최고의 성경 교사로 인식하고 있었습니다. 예수님은 그의 마음을 꿰뚫어 보셨고, 직접적인 대답 대신 그의 마음을 시험하는 말씀을 하셨습니다.
이 말씀의 의미는 간단합니다.
“어떤 희생을 치르더라도 나를 따를 각오가 되어 있는가?”
서기관은 겉으로 보면 희생할 준비가 된 것처럼 보입니다. 그러나 그는 마치 양을 이리 떼 속으로 보내지는 것 같은 운명을 감당해야 한다는 사실을 이해하지 못했습니다. 가족의 반대가 있어도 따라야 한다는 사실을 알지 못했습니다. 예수님을 따른다는 것은 겟세마네, 골고다, 그리고 무덤까지도 함께해야 한다는 의미임을 깨닫지 못했습니다.
이 당시 베드로나 요한조차도 이러한 깊은 이해를 가지고 있지 않았을지 모릅니다. 따라서 서기관에게 그것까지 요구하는 것은 무리일 수도 있습니다. 그러나 최소한,
“여우도 굴이 있고, 공중의 새도 거처가 있으되, 인자는 머리 둘 곳이 없다” 라는 말이 무엇을 의미하는지는 이해해야 했습니다. 그에게는 차분히 생각할 시간이 필요했던 것입니다.
우리도 예수님을 따를 때, 희생을 각오해야 한다고 하면 망설여질 것입니다. 당연합니다. 행복해지기 위해 예수님을 따르려는 것인데, 희생을 요구받으면 망설이는 것은 자연스러운 일입니다. 그러나 한 가지는 확실합니다.
참된 제자는 온 세상을 얻는다 해도 예수 그리스도를 잃는다면 헛되다는 것을 압니다.
예수님이 영원한 생명 그 자체이며, 하나님이심을 알기에 기꺼이 희생을 감수할 수 있는 것입니다. 앞으로 무슨 일이 일어날지 우리는 알 수 없습니다. 하지만 예수님이 함께하십니다. 그 예수님의 손을 붙잡고 나아갈 수 있다고 믿는 것입니다.
또한, 예수님을 어느 정도 깊이 이해하고, 따르기를 원했던 한 제자가 있었습니다. 그는 예수님께 말했습니다.
“주여, 내가 먼저 가서 내 아버지를 장사하게 하럭하옵소서” (21절)
이에 대해 예수님은 허락하지 않으시고, 즉시 따르라고 명령하셨습니다.
“죽은 자들이 그들의 죽은 자들을 장사하게 하고 너는 나를 따르라” (22절)
여러분, 여기서 ‘아버지의 장례’와 관련된 대화를 어떻게 이해해야 할까요?
우리도 부모님의 장례를 치르는 것은 자식의 의무라고 생각합니다. 유대인들에게는 더욱 그러했습니다. 부모를 장사 지내는 것은 단순히 장례식만 의미하지 않습니다. 당시 유대 사회에서 장남은 부모가 돌아가시고 유산을 상속받을 때까지 집을 떠날 수 없었습니다. 그것이 사회적 상식이었습니다.
따라서 이 제자가 한 말은,
“부모님을 장사 지낼 때까지 집에 머물게 해 주세요. 부모님이 돌아가신 후 따르겠습니다.” 라는 의미였을 것입니다. 즉, 그는 사실상 예수님을 따르는 일을 미루고 있었습니다. 그래서 예수님은 “나를 따르라.” 즉, 미루지 말고 지금 결단하라고 말씀하신 것입니다.
더 나아가 예수님은 매우 독특한 표현을 사용하셨습니다.
“죽은 자들이 그들의 죽은 자들을 장사하게 하라.”
예수님께서 부모의 장례를 소홀히 여기신 것이 아닙니다. 다만, 이 제자는 예수님을 따르기로 결심하기 전에 속해 있던 세상이, 더 이상 자신이 머물러야 할 곳이 아님을 깨달아야 했습니다.
“죽은 자들이 그들의 죽은 자들을 장사하게 하라” 라는 말씀은, 그가 이전에 속해 있던 세상은 죄로 인해 죽을 운명에 처한 세상이라는 의미일 것입니다.
예수님을 따른다는 것은, 하나님께서 인간을 멸망에서 구원하시고 생명으로 옮기신 데 대한 우리의 응답입니다. 그러므로 구원을 얻기 위해서는 무엇보다도 하나님께서 보내신 구원자 예수 그리스도를 최우선으로 해야 합니다.
우리도 서기관처럼 자기중심적인 생각에서가 아니라, 또한 한 제자처럼 세상의 얽매임에 머뭇거리지 않고, 예수 그리스도만이 생명의 길임을 믿고 온전히 예수님을 따르는 삶을 살아갑시다.