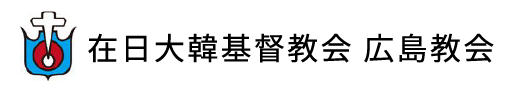2025年03月23日 主日礼拝 式順・説教
2025年3月23日 主日礼拝 式順・説教
〇黙 祷
〇招 詞 マルコ(마가복음) 9章 23節
〇讃 頌 讃頌歌 26
〇信仰告白 使徒信条
〇祈 祷
〇交 読 文 交読文 126 (四旬節 [3] )
〇讃 頌 讃頌歌 263
〇聖書奉読 マタイによる福音書(마태복음)
9章 18~26節
〇説 教 「信仰を発揮するならば(믿음을 발휘한다면)」
〇祈 祷
〇讃 頌 讃頌歌 282
〇奉献祈祷
〇献 金
〇交 わ り
〇頌 栄 讃頌歌 6
〇祝 祷
※ 説教映像をYouTubeでご覧いただけます。
【 2025年 3月 23日 主日礼拝説教(要約版)】
「信仰を発揮するならば」
マタイによる福音書 9章 18~26節
先週の聖書箇所は、新しいぶどう酒を受け入れるためには、新しい革袋が必要であるという内容でした。新しい革袋というのは、教会や私たち自身のことを意味しておりますが、神さまの新しい祝福(福音)を受け入れるためには、いつも、私たちが聖書、神さまの御言葉によって新たにされなければならないとお話しました。この新しい革袋の話をイエスさまが話されていた時、そこに「ある指導者」がやって来て、イエスさまにこのように言いました。「わたしの娘がたったいま死にました。でも、おいでになって手を置いてやってください。そうすれば生き返るでしょう。」(18節))
「ある指導者」というのは、他の福音書によれば会堂長ヤイロだと言います。彼はイエスさまを敵対視していたファサイ派に属していたかもしれません。そんな彼がイエスさまの前にひれ伏すとは、彼の必死さがよく表れています。「手を置いてやってください。そうすれば生き返るでしょう。」
「死んだ娘を生き返らせて欲しい」と言うわけですが、普通ではあり得ない要求です。それくらい必死だったとはいえ、イエスさまに無理難題を押しつけているとしか言えません。それが信仰と言えるのか、という疑問もあります。
それでも彼は、同僚のファリサイ派の人々が見ている中で、すべてのプライドを捨てて、へりくだって、そして真剣にイエスさま懇願しているのです。「ひれ伏して」というのは礼拝を意味しています。イエスさまを神さまとして、最後の祈りをささげているのです。この後、どうなるのかとかは考えていません。娘を十二年間、愛情を注ぎ育ててきました。当時のユダヤ社会では、女性が満12歳を迎えれば、一人前の大人とみなされ、結婚が許される年齢です。人生これからという時に死ぬなんて父親として認めたくありません。娘のために何とかしてあげたい。父親の必死な思いです。
イエスさまは彼の信仰に応えようとして、彼のあとをついて行かれました(19節)。「ついて行く」イエス・キリスト。この何気ないこの表現中にも、キリストの憐れみと愛を感じ取ることができます。ある指導者とキリスト、そして弟子たちは、死人のいる家に向かって進んで行きます。この一行を誰にも邪魔して欲しくありません。しかし、イエスさまを取り巻く群衆が放って置くはずがありません。大勢の人がついて行きました。
その中に、重い病を負った一人の女性がおりました。彼女は12年間も病を患い出血が止まらずに苦しんでいました。指導者の娘が12年間、親に愛され、日向を歩んでいた時、反対に日影を歩み、涙にくれていたのです。彼女の病は、家族からも隔離されなければならないという種類のものでした。彼女は病のために汚れていると見做され、家族にも近づくことの出来ない、社会的に隔離された、まさに孤独の身であったのです。彼女は、この病を癒やすために全財産を使ったと言います。彼女は孤独の問題だけではなく、経済的には破綻し、そして肉体的には絶望という状態にありました。それは死んだも同然のような状態でした。それでも、彼女には信仰が残っていたようです。
彼女は驚くべき行動に出ました。それは聖なる方に触れるという行為です。しかも、イエスさまの後ろから誰にも気づかれないようにイエスさまの服に触れたのです。彼女がこのような行動をとったのは、もちろん、自分が汚れた者であるから、堂々正面切って願えないということもありましたが、それ以上に、「『この方の服に触れさえすれば治してもらえる』と思ったから」(21節)です。
これまで人々は、様々な方法で信仰を働かせてきました。「主よ、御心ならば…」(8:2)、「ただ、ひと言おっしゃってください。そうすれば…」(8:8)、「おいでになって手を置いてやってください。そうすれば…」(8:18)。でも、面と向かってお願いすることもできません。お言葉を受けることも申し訳ない気がします。かといって何もしなかったら、何も起こりません。そのため、彼女はイエスさまの服に触れることを思いつきました。この方法がベストであったかどうかは別として、信仰の強さは一級品です。これは他に人に知られたらまずい、礼儀のない行為に映るだろうし、服にさわれば直るという信念は迷信的なものにも映ります。けれども、イエスさまはそれらを一切非難することなく、彼女の信仰に目を留め、暖かい言葉をかけました。「娘よ、元気になりなさい。あなたの信仰があなたを救った。」(22節)
彼女の病を癒やしたのは、イエスさまですが、イエスさま対する信仰が癒やしたと言うことも事実です。イエスさまは彼女の信仰を賞賛しています。
信仰を働かせる方法は様々です。聖書を見ますと、イエスさまにに食い下がって、断られてもあきらめようとしない異邦人女性の話も出てきますし、言葉も発せず、後ろから近づく彼女のような人もおります。しかし共通するのは、イエスさまにはできる、と信じる信仰です。イエスさまは宣言されました。「あなたの信仰があなたを救った」。
彼女は、肉体的に救われたばかりではなく、霊的にも救われました。これを機に彼女は孤独から解放され、社会生活に復帰し、普通の生活を営むようになっていったでしょう。何よりも、喜びと賛美をもって主に仕える者となったと思います。
それから、イエスさまが指導者の家に行きますと、そこには「笛を吹く者たちや騒いでいる群衆」(23節)がおりました。ユダヤの慣習では、人が死ねば、笛吹く者たちと泣き女たちを雇い、家族の悲しみの感情を表わしました。葬儀にはそのような演出がなされていましたが、これから起こることを考えれば、このような演出は全く無用でした。「あちらに行きなさい。少女は死んだのではない。眠っているのだ」(24節)と、騒いでいる人々を追い出し、静かになった環境で少女を生き返らせました。
今日の聖書箇所では、これまでにない幾つかのことを見ることができます。イエスさまはこれまで、病気を癒やし、悪霊を追い出し、嵐を鎮め、キリストの権威というものを示して来られました。しかし、それで終わりません。今日の聖書箇所では、最後の敵である死に対してもキリストの権威を発揮されました。
キリストの死に対する権威は、やがてご自身の復活において明瞭に証されることになります。人間の死というのは、聖書において、人間の罪の必然的結果として描写されています。しかし、キリストの福音、キリストの命は、これを打ち砕きます。新しいぶどう酒であるキリストの福音、キリストの命は、古い皮袋を許しません。この場面では、過去の葬儀の姿を許さないということです。
そして、今日の聖書箇所において、社会階級の高い指導者と階級社会から追放された一人の女性が並列に描かれていることは、信仰と言うものが、社会階級の別、貧富の別、学識の別、そういったことと一切関係ないということです。それはまた、信仰を発揮し、祝福に与る機会は誰にでも与えられているということです。
この指導者が信仰を発揮しなかったらどうなっていたでしょうか。12歳になった娘が死ななければならないということだけでなく、この家庭に祝福がもたらされることはなかったということです。生き返った娘は生涯、キリストに従う者となったでしょう。12年間患って出血が続いていた女性は、信仰を発揮したがゆえに、体の癒やしや社会復帰に与ったばかりではなく、永遠の命をいただくことができたはずです。もし彼女が信仰を発揮しなかったら、孤独に日影の生活を送り続け、肉体、精神がボロボロになって、数年後に社会の片隅で、汚れた女性として人生を終えていたかもしれません。しかし、今や、彼女は、二千年の長きに渡って、聖書の記述を通して、人々を励ます存在となりました。
皆さん、信仰は発揮しなかったら損です。皆さんも、その眼差しをキリストに向け、信仰を発揮し、皆さんの個人史に信仰の物語を刻んでいただきたいと願います。また、その証を互いに分かち合い、ともに励まされ、信仰の家族として歩んで行きましょう。
【2025년 3월 23일 주일예배(요약판)】
“믿음을 발휘한다면” 마태복음 9장 18~26절
지난주 성경 말씀에서는 새로운 포도주를 담기 위해서는 새로운 가죽 부대가 필요하다는 내용이었습니다. 새로운 가죽 부대란 교회와 우리 자신을 의미하며, 하나님의 새로운 축복(복음)을 받아들이기 위해서는 우리가 항상 성경, 곧 하나님의 말씀으로 새로워져야 한다는 것을 말씀드렸습니다.
예수님께서 이 새로운 가죽 부대에 대해 말씀하고 계실 때, 한 관리가 예수님께 와서 간청하였습니다. “내 딸이 방금 죽었사오니 오셔서 그 몸에 손을 얹어 주소서 그러면 살아나겠나이다”(18절)
이 “한 관리”는 다른 복음서에 따르면 회당장 야이로입니다. 그는 바리새인에 속해 있었을 가능성이 있으며, 예수님을 적대시하는 입장이었을 수도 있습니다. 하지만 그는 자신의 모든 체면과 자존심을 내려놓고, 예수님 앞에 엎드려 간청하였습니다. “손을 얹어주소서 그러면 살아나겠나이다”.
이것은 상식적으로 있을 수 없는 요청이었습니다. 딸이 이미 죽었는데, 살아나게 해 달라는 것입니다. 아무리 다급한 상황이라도, 이는 도저히 가능할 것 같지 않은 요구였습니다. 과연 이것을 믿음이라고 할 수 있을까요?
그러나 그는 주변에 바리새인들이 지켜보는 가운데서도 자신의 모든 자존심을 내려놓고, 겸손히 엎드려 간절히 예수님께 간청하였습니다. 여기서 “절하며”라는 표현은 예배를 의미합니다. 즉, 그는 예수님을 하나님으로 인정하고 마지막 희망을 걸고 기도하고 있는 것입니다. 이후 일이 어떻게 될지 생각할 겨를도 없이, 그는 그저 딸을 살리고 싶은 아버지의 간절한 마음으로 예수님께 매달린 것입니다.
유대 사회에서 여자아이가 만 12세가 되면 성인이 되어 결혼이 허락되는 나이가 됩니다. 이제 막 인생을 시작하려던 딸이 세상을 떠난다는 것은 아버지로서 도저히 받아들일 수 없는 일이었습니다. 딸을 위해 무엇이라도 하고 싶은, 아버지의 필사적인 사랑이 여기에 담겨 있습니다.
예수님께서는 그의 믿음에 응답하시기 위해 그와 함께 가셨습니다. “예수께서 일어나 따라가시매 제자들도 가더니”(19절)
이 구절을 보면, 예수님께서 단순히 함께 가신 것이 아니라 “따라가셨다”는 표현이 사용되었습니다. 이는 예수님의 깊은 긍휼과 사랑을 보여 주는 대목입니다. 예수님과 제자들, 그리고 이 관리는 죽은 소녀가 있는 집을 향해 걸어갑니다. 아무도 이들을 방해하고 싶지 않았을 것입니다. 그러나 예수님을 둘러싼 군중들은 그들을 가만히 두지 않았습니다.
그 군중들 사이에 12년 동안 혈루증으로 고통받던 한 여인이 있었습니다. 그녀는 끊임없는 출혈로 인해 큰 고통을 겪고 있었습니다. 회당장의 딸이 12년 동안 부모의 사랑을 받으며 빛 속에서 살아왔던 반면, 이 여인은 같은 12년 동안 어둠 속에서 눈물로 살아왔습니다.
당시 율법에 따르면, 그녀와 같은 병을 가진 사람은 부정한 자로 간주되어 가족과도 떨어져 살아야 했습니다. 그녀는 병 때문에 더럽다고 취급받았고, 가족과 사회로부터 격리된 채 철저한 고독 속에 살아야 했습니다. 또한, 병을 고치기 위해 전 재산을 다 써버렸지만 아무런 소용이 없었습니다. 그녀는 육체적으로뿐만 아니라 경제적으로도 완전히 파산한 상태였습니다. 이제 남은 것은 오직 절망뿐이었습니다. 사실상 그녀는 죽은 것이나 다름없는 삶을 살고 있었습니다. 그럼에도 불구하고, 그녀에게는 한 가지 남아 있었습니다. 그것은 바로 믿음이었습니다.
“그 겉옷만 만져도 구원을 받겠다”(21절). 이것이 그녀의 믿음이었습니다. 그녀는 예수님의 옷자락을 만지기로 결심합니다. 이 그녀의 믿음이 진짜 믿음인지 판단이 어렵습니다만, 예수님께서는 그녀의 믿음을 책망하지 않으시고, 오히려 칭찬하셨습니다. “예수께서 돌이켜 그를 보시며 이르시되 딸아 안심하라 네 믿음이 너를 구원하였다 하시니 여자가 그 즉시 구원을 받으니라”(22절).
그녀의 병을 치유하신 분은 예수님이십니다. 그러나 그녀가 믿음을 발휘했기에 치유가 이루어진 것입니다. 예수님께서는 그녀의 믿음을 칭찬하셨습니다.
한편, 예수님께서 관리의 집에 도착하셨을 때, 장례식이 진행되고 있었습니다. 유대인의 장례 문화에서는 피리를 부는 사람들과 곡하는 사람들이 고용되어 가족의 슬픔을 표현했습니다. 그러나 예수님께서는 그들을 내보내시며 말씀하셨습니다. “물러가라 이 소녀가 죽은 것이 아니라 잔다”(24절).
사람들은 예수님의 말씀을 듣고 비웃었습니다. 그러나 예수님께서 소녀의 손을 잡으시자 그녀는 일어났습니다. 25절입니다. “무리를 내보낸 후에 예수께서 들어가사 소녀의 손을 잡으시매 일어나는지라”(25절).
오늘 본문을 통해 우리는 예수님께서 질병뿐만 아니라 죽음까지도 다스리시는 권위를 가지셨음을 알 수 있습니다. 예수님께서 죽음을 이기신 권세는 훗날 자신의 부활을 통해 명료하게 증명됩니다. 인간의 죽음은 성경에서 인간의 죄의 필연적 결과로 묘사됩니다. 그러나 그리스도의 복음, 그리스도의 생명은 이를 깨뜨립니다. 새 포도주인 그리스도의 복음, 그리스도의 생명은 오래된 가죽부대를 허용하지 않습니다. 이 장면에서는 과거의 장례 의식을 용납하지 않는다는 의미입니다.
또한, 본문에는 사회적으로 높은 지위에 있던 관리와, 사회에서 소외된 한 여인이 등장합니다. 이를 통해 믿음은 사회적 신분, 재산, 학식과는 무관하며, 누구에게나 동일한 기회가 주어진다는 사실을 보여줍니다.
만약 관리가 믿음을 발휘하지 않았다면 어떻게 되었을까요? 12살된 그의 딸은 죽어야만 했을 것이고, 그의 가정에 축복이 임하지도 않았을 것입니다. 혈루증을 앓던 여인도 믿음을 발휘했기에 육체적인 치유와 사회적 경험을 회복했을 뿐만 아니라 영원한 생명까지도 받았던 것입니다. 만약 믿음을 발휘하지 않았더라면 외롭게 숨어사는 삶을 지속하다가 육체와 정신이 피폐해진 채 평생 사회의 변두리에서 부정한 여인이라는 낙인 속에 고립되어 불행하게 삶을 마감했을지도 모릅니다. 그러나 그녀는 지금까지도 성경을 통해 수많은 사람에게 용기와 희망을 주는 믿음의 본이 되고 있습니다.
사랑하는 성도 여러분, 믿음을 발휘하는 것은 매우 중요합니다. 하나님 앞에서 믿음을 발휘할 때, 하나님의 놀라운 역사가 나타날 것입니다. 우리도 예수님을 바라보며 믿음을 실천하고, 삶 속에서 믿음의 역사를 경험하기를 바랍니다. 그리고 그 믿음의 간증을 함께 나누며 하나님의 가족으로서 함께 걸어갑시다. 아멘.